オンライン診療を受けるあなたへ──「電子カルテ×予約システム連動」って何が便利なの?使い方ガイド
スマホで病院を予約して、そのままオンライン診療を受ける。もう当たり前になりつつあります。特に「予約システム」と「電子カルテ(カルテ)」が連動していると、患者側にとってもメリットが増えます。ここではオンライン診療を使う患者向けに、「連動の利点」「実際の使い方」「注意点」「便利に使いこなすコツ」を現場目線でわかりやすく解説します。
まず一言:連動って何がいいの?
予約時に入力した基本情報や事前問診の回答が、そのままクリニックの電子カルテに自動で反映されます。つまり、受付で同じことを何度も言わなくていい、診察時間が無駄にならない、過去の診療情報や検査結果を医師がすぐ参照できる――という具合に「手間が減る+診療の質が上がる」利点があります。多くの導入クリニックはオンライン問診やファイル送信(保険証や検査画像の送付)にも対応しています。
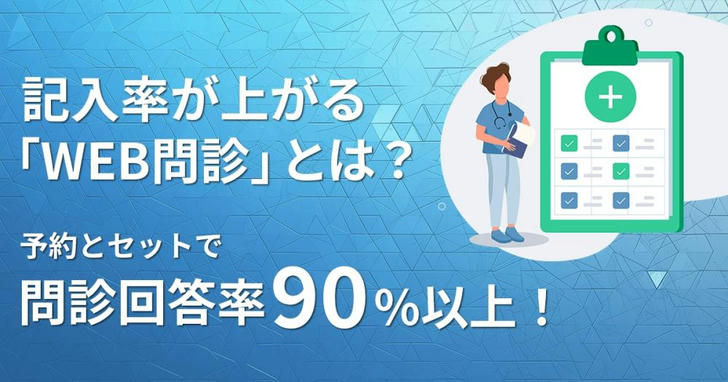
患者のための「オンライン診療利用フロー」(実践)
1.アプリ/サイトでクリニックを検索: CLINICSのようなプラットフォームや、クリニックの予約ページでオンライン診療可を確認。
2.アカウント登録&予約: 氏名・生年月日・連絡先を登録。保険証は写真アップや事前提出が求められることが多い。
3.事前問診に回答: 症状や既往歴、服薬状況を入力。これがカルテに反映されると医師が診察前に確認できます。
4.オンライン診療(ビデオまたは電話): 時間になったらアプリでビデオ通話。問診や視診、必要な指示(検査や処方)が行われます。
5.会計・処方の受け取り: キャッシュレス決済対応クリニックならアプリで支払い、処方は電子処方箋や薬局への送信で受け取れます(方式は施設により異なります)。
具体的にどんなメリットがある?
🔹待ち時間短縮: 事前問診で診察準備ができるため診療がスムーズ。
🔹継続的な診療管理: 受診履歴や検査結果がカルテに残るので、次回以降の診療がスムーズ。
🔹書類・画像のやり取りが楽: 保険証や検査結果の写真をそのまま送れるサービスがある。
利用時のチェックポイント(安全&トラブル回避)
1.ID確認・保険証の扱い: 保険証の提出方法や本人確認の手順を事前に確認しましょう(写真アップやオンライン確認が一般的)。
2.プライバシーと通信の安全性: 医療データは機微情報です。暗号化やログ管理、運用ポリシーが整っているサービスを選ぶのが安心です。導入実績の多いプラットフォームは管理体制を公開しています。
3.決済・処方の受け取り方法: 会計がオンラインか窓口か、処方は電子処方箋か紙か、薬局受け取りの手順を確認しておくと受診後がスムーズ。
4.対応範囲の確認: 初診でオンライン診療できる診療科や、重症時の対面受診の必要性については各クリニックの案内を確認。症状によっては対面を案内されます。
どんなサービスがある?(代表例)
🔸CLINICS(メドレー): 予約・問診・オンライン診療・決済・ファイル送受信がまとまったプラットフォーム。利用可能な医療機関をアプリで検索できます。
🔸Medical Reserve(メディカル革命 by GMO): 予約→来院チェックイン→電子カルテ連携まで対応するシステムで、多数の医療機関が導入しています。
(どのクリニックがどの機能に対応しているかは、各サービスの診療ページで確認してください。)
オンライン診療を“より便利に”使うコツ
🔹事前に問診を丁寧に書く: 医師の診察準備がしやすくなり、的確な処方や指示を受けやすくなります。
🔹保険証・服薬情報・過去の検査画像を手元に: 必要時にすぐアップロードできると診療が早く終わります。
🔹トラブル時の連絡先を控える: 通信が途切れた場合や予約変更時に備え、クリニックの連絡方法を確認しておきましょう。
よくある質問(Q&A)
Q:オンライン診療で処方はもらえますか?
A:多くのクリニックで可能です。処方の受け取り方法(電子処方箋・薬局送付・窓口受け取り)は医療機関によって異なるので、予約時に確認してください。
Q:高齢の家族でも使えますか?
A:可能ですが、操作が難しい場合は家族が代理で予約や問診入力を行う、あるいは簡易な電話対応のオンライン診療を提供する施設を探すとよいでしょう。事前にサポートの有無を確認してください。
最後に
スマホで「CLINICS」や「オンライン診療 対応病院」を検索して、近隣でオンライン診療を行う医療機関を探してみましょう。
予約ページで**「オンライン診療の可否」「保険証の提出方法」「処方の受け取り方法」**をチェック。事前に準備しておけば、診療はぐっとスムーズになります。
